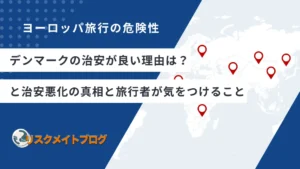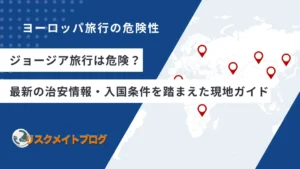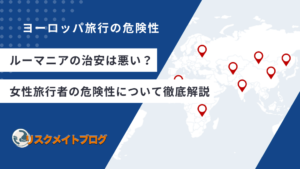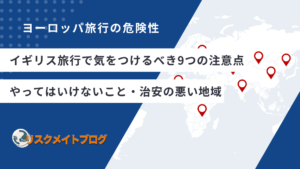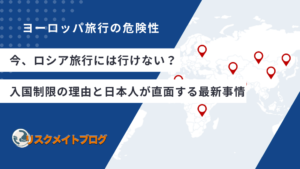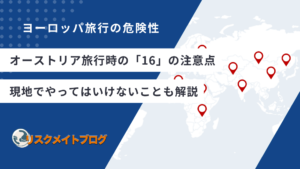透明度の高い湖と雄大なアルプス、時計やチョコレートで有名な国「スイス」
整ったインフラと自然の美しさ、治安の良さで「旅行しやすい国」として常に高い人気を誇っています。
特に日本人旅行者からは、「時間通り」「清潔」「安全」というイメージが強く、初めてのヨーロッパ旅行先として選ばれることも少なくありません。
しかし、実際に訪れてみると「思ったより不便だった」「気をつけることが多かった」と感じる人も意外と多いのがスイスです。美しさの裏には、観光客が気付きにくい「ルールの厳しさ」や「予想外の出費」、「治安の落とし穴」も存在しているのです。
この記事では、スイス旅行で注意すべき基本マナーから、意外な悪いところ、最新の治安情報まで徹底的に解説します。これからスイスに行く人が、快適で安心な旅を楽しめるように、現地でのリアルな注意点を一つずつ紹介していきます。
スイス旅行でしてはいけない基本的な注意点

スイスは法やマナーに対する意識が非常に高い国であり、「知らなかった」では済まされないルールが多く存在します。
この章では、観光客が特に気をつけるべき日常のマナーやNG行為について紹介します。小さな違反が現地での信頼を損ねる原因になったり、罰金の対象になることもあるため、事前の知識がとても重要です。
電車やトラムで打刻しない
スイスの公共交通機関では、チケットを購入するだけでは乗車の権利を得たことにならない場合があるという点に注意が必要です。
特に「時間制の乗車券(ゾーンチケット)」や「回数券」を利用する場合は、乗車前または車内に設置された「打刻機」で日時をスタンプする(打刻する)ことが義務づけられています。
この打刻を怠ると、たとえ有効なチケットを持っていたとしても、無賃乗車と見なされて罰金を請求されることになります。実際に、旅行者が知らずに乗車してしまい、100フラン(約1万6000円)以上の罰金を払った例も少なくありません。
特に都市部では抜き打ちの検札も頻繁に行われているため、「買ったから安心」ではなく、「打刻したか?」を確認する習慣をつけておきましょう。
公共の場での大声や電話は避ける

スイス人は、プライバシーと静けさをとても大切にする国民性を持っています。そのため、電車やトラム、カフェ、レストランなどの公共の場で、声のボリュームが大きい人や電話で会話している人に対して強い違和感を持つ人も多いです。
実際に、駅のホームやバスの中で、外国人観光客が大きな声で話していると、周囲が露骨に迷惑そうな表情をする場面もよく見られます。
日本のように「周囲に配慮して静かにする文化」が根づいている一方、スイスではそれが社会のルールとしてしっかり共有されているのです。
そのため、スマートフォンでの通話や大声での会話は避け、静かに過ごす姿勢が現地での好印象に繋がります。
ホテル・アパートでのシャワー音や足音
スイスでは、生活音に対する感覚がとても敏感で、ホテルや民泊(アパートメント滞在)では特に注意が必要です。
たとえば、夜間(22時〜翌朝7時)は「静寂タイム」とされており、この時間帯にシャワーの音や床を歩く音、テレビの音量が気になるという苦情が住人から出ることがあります。
日本では問題視されないレベルの音でも、スイスでは「マナー違反」として扱われることがあり、場合によっては管理会社から注意を受けたり、追加料金が発生することすらあるのです。
特に木造の古い建物や、アパートメントタイプの宿泊先では、階下や隣室に音が響きやすい環境があるため、夜間の入浴・荷物の整理・ドライヤーの使用には十分な配慮が求められます。
日曜・祝日に買い物に行ってもお店はclosed
スイスでは、日曜日や祝日はほとんどの商業施設が休業するというルールが今も厳格に守られています。
これは「家庭や休息の時間を大切にする」という文化が背景にあり、観光客にとっては少し不便に感じる瞬間でもあります。
たとえば、大型スーパーやショッピングモールはもちろん、パン屋・ドラッグストア・服飾店なども軒並み閉まってしまうため、「あ、日曜だった…」と食事や日用品の調達に困る人も多いのです。
対応策としては、土曜日のうちに必要な買い物や食料品をしっかり買い揃えておくことが基本です。どうしても必要なときは、大都市の中央駅構内にある「日曜営業のミニスーパー」やガソリンスタンド併設のショップが頼りになりますが、価格はやや高めです。
ゴミの分別違反
スイスのゴミ分別ルールは、非常に厳格で徹底されています。
紙、プラスチック、ガラス、生ゴミなどがきっちり分けられており、それぞれ専用の回収ボックスや曜日が決まっています。
また、家庭ゴミを出す際には、「指定の有料ゴミ袋(税金込み)」を使わなければならない地域も多く、観光客が民泊で滞在する場合には特に注意が必要です。
分別が適切でなかった場合、ホストに迷惑がかかるだけでなく、罰金の対象になるケースもあるため、チェックイン時に必ず「ゴミの捨て方」について確認するようにしましょう。
短期滞在でも、「ちょっとぐらいなら…」という感覚は通用しません。環境意識が高く、マナーに厳しいスイスだからこそ、リスペクトを忘れない行動が必要です。
カード主流でも「現金不可」な場面が一部存在
スイスはキャッシュレス化が進んでおり、クレジットカードやデビットカードが使える場所が非常に多い国です。特に都市部では、レストラン、ホテル、交通機関、商店のほとんどでタッチ決済が利用できます。
しかしその一方で、地方や小規模な屋台、公共トイレ、コインロッカー、山小屋などでは「現金のみ」の場所が今でも存在しているため注意が必要です。
特にスイスでは「5フラン硬貨」「10フラン紙幣」などが日常的に使われており、観光客が困らないためにも、滞在中は小額の現金を常備しておくと安心です。
両替は空港や駅よりも、街中の銀行の方がレートが良いことも多いので、滞在初日にある程度のスイスフランを確保しておくとスムーズです。
個人宅や子ども・教会内での撮影
スイスでは「プライバシーの保護」が非常に重視されており、撮影に関しても厳しいマナーが存在します。
たとえば、美しい街並みを撮影しているつもりでも、個人宅やナンバープレートが写り込んでいるとトラブルの原因になることがあるのです。
また、子どもを無断で撮影する行為は完全にNGであり、たとえ遠目からでもカメラを向けると保護者に不快感を与えたり、通報されることもあります。
同様に、教会内部では撮影禁止の場所も多く、静粛を求められる場でフラッシュを使うなどの行為は失礼に当たるため、事前に案内板や係員の指示をよく確認しましょう。
美しい景色を記録に残したい気持ちは自然なことですが、その場にいる人々や文化への敬意を忘れない撮影マナーが、トラブルの回避につながります。
知ってた?スイスの意外な「悪いところ」
整備された街並みと絶景の自然、清潔で安全な環境——スイスには「完璧」なイメージがつきまといます。
しかし、実際に訪れてみると、「え?ここが不便?」「こんなに高いの?」と驚くポイントも少なくありません。
この章では、観光パンフレットでは語られにくい、スイスの「意外と知られていないデメリット」について正直に解説します。
物価が世界トップクラスに高く、気軽な食事も高額になる
スイスといえば、美食の国という印象を持つ人もいるかもしれませんが、旅行者にとってもっとも現実的な「壁」になるのがその物価の高さです。
たとえば、街中のカフェで軽くランチをしようとすると、サンドイッチとドリンクだけで2,000円相当になることも普通です。
レストランでディナーを楽しもうものなら、メイン1品+ドリンクで日本円にして5,000円を超えることも珍しくありません。
「ちょっとした食事=高級外食」という認識が必要で、旅の予算を圧迫する大きな要素となるのは間違いないでしょう。
節約したい場合は、スーパー(CoopやMigros)でデリを買ってホテルで食べる、現地のマルシェを利用する、ピクニックスタイルのランチを楽しむといった工夫が重要です。
食事にかけるお金と楽しみのバランスを自分なりに見つけることが、スイス旅行を成功させるコツでもあります。
日本のような「お詫び文化」はない
日本では、ちょっとしたミスにも「申し訳ありません」と丁寧に謝罪する文化がありますが、スイスでは「謝らない文化」が一般的です。
たとえば、ホテルのチェックインで部屋の準備ができていなかったり、注文した品と違う料理が出てきたときも、スタッフは謝罪ではなく「仕方ないよね」というリアクションを返すことが多いのです。
これはサービスが悪いというより、「完璧を求めすぎない」というスイス人の価値観が背景にあります。
相手に過剰な責任を問わず、ミスはお互いさまという意識が強いため、「ごめんなさい」がすぐに返ってこなくても怒らないことが旅をスムーズに進めるカギとなります。
自分が間違えたときも、「謝罪よりも行動でカバーする」姿勢が好まれ、文化の違いを理解することがストレスの軽減につながります。
医療費・救助費が超高額
絶景の山々が魅力のスイスでは、ハイキングやスキーなどアウトドアを楽しむ人も多いですが、万が一の事故や病気が発生した場合、現地での医療費や救助費は驚くほど高額になる可能性があります。

たとえば、山で転倒してヘリで救助されるようなケースでは、数十万〜100万円を超える費用が請求されることも珍しくありません。
また、風邪や腹痛で病院を訪れるだけでも、診察料・薬代が日本の何倍にもなることがあります。
これを防ぐためには、海外旅行保険への加入が必須。特に「スイスでの救助費用」がカバーされる内容を選ぶことが重要です。
スイスでは「何があっても自己責任」という考えが根付いているため、備えのない旅行者が大きな損をしてしまうリスクもあるのです。
スイスの治安は悪化してる?見えにくい落とし穴を解説
スイスと聞くと、まず「安全な国」というイメージを思い浮かべる方が多いでしょう。実際、世界の治安ランキングでも常に上位に位置し、街並みも整然としており、夜の一人歩きでも怖さを感じない国です。
しかし、それでも「100%安全」というわけではありません。特に観光客として訪れる場合、「見えにくいリスク」や「油断しやすい場所」にはしっかり注意する必要があります。
この章では、スイスにおける最新の治安情報と、旅行者が気をつけるべきポイントを丁寧に解説していきます。
外務省の危険情報はなし!

2025年現在、日本の外務省が発表するスイスに関する海外安全情報では、危険レベルは「0」=特別な注意は不要とされています。
この評価は、政治的安定性・犯罪発生率・警察や行政の信頼度など、総合的に見て非常に良好な国であることを表しています。
実際に現地に足を運んでも、人々は穏やかで公共の場も清潔。ATMでの現金引き出しや夜間の移動など、他国ではためらうような行動も比較的安心してできるのがスイスの魅力です。
とはいえ、これはあくまで「基本的な社会の安全性」であり、観光客にとっての「狙われやすい場所」や「注意すべき行動」がゼロではないことは認識しておくべきです。

スリ・置き引きは観光都市や駅構内で発生している
スイスでもっとも多い犯罪の一つが、スリや置き引きといった「軽犯罪」です。
これらはチューリッヒ中央駅やジュネーブ空港、ルツェルンの旧市街など、外国人観光客が多く集まる場所で特に発生しやすいとされています。
手口としては、混雑するトラム内でバッグのチャックを開けられる、ベンチに置いたリュックから財布を抜き取られる、カフェで荷物を足元に置いていて盗られるなど、「ほんの一瞬の油断」が命取りになります。
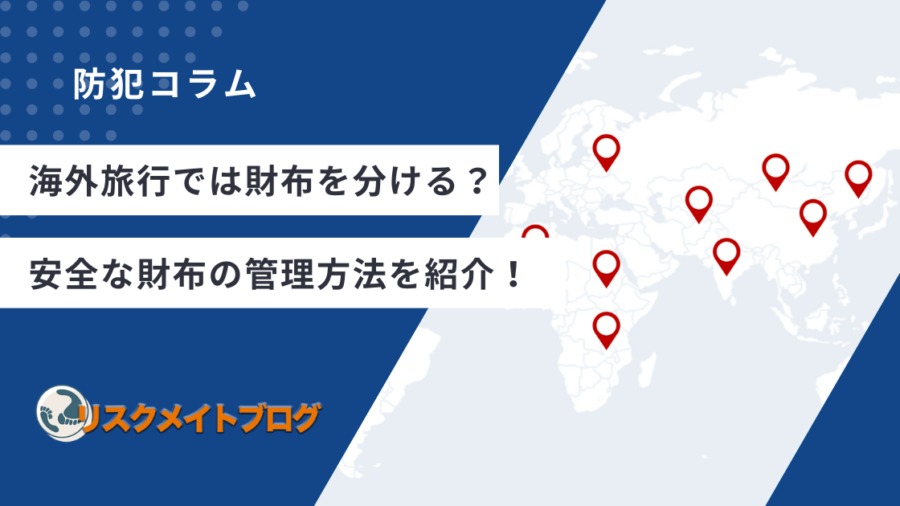
また、近年はグループで連携して観光客を囲むようにしてスリを働く手口も増えており、「人が多い=安全」ではなく、「人が多い=狙われやすい」と認識を改める必要があります。
荷物は常に体の前で管理し、チャック付きのカバンやウエストポーチなどを活用することで、被害のリスクを大きく下げることが可能です。

山エリアでは遭難・事故のリスクも
スイス旅行の大きな楽しみの一つが、アルプス山脈を中心とした大自然でのハイキングやトレッキングです。
ですが、その美しい風景の裏には、想像以上に厳しい自然環境と、油断すると命に関わるリスクが潜んでいます。
- 登山ルートでの方向ミスによる遭難
- 天候急変による滑落や低体温症
- 無理なスケジュールでの体力消耗と高山病
- 適切な装備なしでの登山による転倒や怪我
スイスの山は整備されているように見えても、一歩間違えば「救助が必要な状況」に陥る場所も多く存在しています。
旅行者の中には「観光地感覚で登れる」と思い、運動靴や軽装で挑んでしまう人もいますが、現地の人は皆しっかりした装備で挑んでいます。
無理せず、ガイド付きツアーを利用する・事前に天気とルートを確認する・緊急時の連絡手段を確保するといった備えが大切です。
スイス旅行を快適に過ごすためのコツ
ここまででスイス旅行の注意点や治安情報をお伝えしてきましたが、少しの準備と心構えで、スイスの旅は驚くほど快適に、そして豊かに楽しむことができます。
この章では、実際の旅を「もっと快適にするためのコツ」を、現地経験者の視点でまとめました。スイスらしい時間の流れにうまく乗るための、小さな工夫をお届けします。
スイスパス・半額カードは早めに購入する

スイス国内を電車やバスで移動するなら、まず検討すべきなのが「スイスパス(Swiss Travel Pass)」や「ハーフフェアカード(Half Fare Card)」です。
スイスの公共交通は整備されていますが、その分運賃が高額。例えば、都市間の電車移動や登山列車などを利用すれば、あっという間に数万円が飛んでしまうこともあります。
スイスパスは、電車・バス・船・トラムなどのほとんどが乗り放題になる便利なフリーパス。美術館などの入場料も割引されるため、観光重視の旅行には特におすすめです。
一方で、ハーフフェアカードはすべての運賃が50%になるお得な割引カード。滞在日数が少ない、または移動が少なめという方に向いています。
どちらも公式サイトや旅行代理店で事前に購入しておくと安心かつ割安になることもあるため、旅のスケジュールに合わせて賢く選びましょう。
現地語(ドイツ語・フランス語)でのあいさつを覚える
スイスには4つの公用語がありますが、旅行者が多く訪れる都市では主にドイツ語とフランス語が使われています。
チューリッヒやルツェルン、ベルンはドイツ語圏、ジュネーブやローザンヌはフランス語圏というように、地域によって言語が切り替わるのがスイスの特徴です。
英語は多くの人に通じますが、「こんにちは(Grüezi/Bonjour)」や「ありがとう(Danke/Merci)」といった基本的なあいさつを現地語で言うと、それだけでとても喜ばれるのがスイスです。
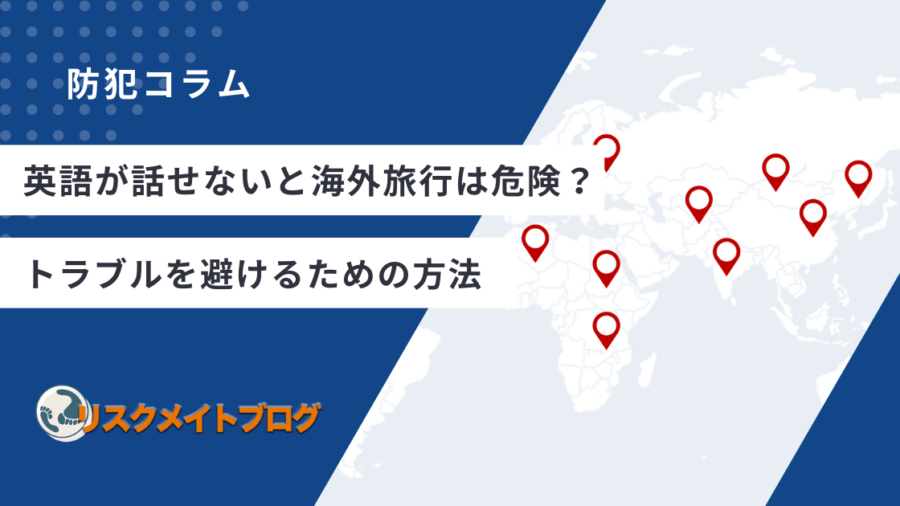
また、レストランでの注文時やホテルのチェックインなどで現地語の一言を添えるだけで、対応がぐっと親切になることもよくあります。
簡単な単語でも心を込めて伝えることが、スイスの「静かだけど温かい」人々との信頼関係を築く一歩になるはずです。
まとめ|注意点を理解してスイス旅行を楽しもう!
スイスは、アルプスの大自然と洗練された都市が調和する、美しさと快適さを兼ね備えた国です。治安も良く、インフラも整い、初めてのヨーロッパ旅行にもぴったりな行き先といえます。
しかしその一方で、「マナーに厳しい社会」「物価の高さ」「文化的なギャップ」といった、日本とは異なるルールや常識も少なくありません。
今回の記事で紹介したように、スイス旅行を成功させるためには、
- 公共交通や宿泊施設でのルールや静粛マナーの理解
- 日曜休業やゴミ分別などの生活習慣の違いへの対応
- スリや山での遭難など、観光客特有のリスクへの備え
- 高額な物価や医療費に対する心構えと事前準備
など、あらかじめ「知っておくべきこと」がいくつもあります。
しかしそれらを踏まえた上で旅をすれば、スイス旅行を心から楽しめるはずです。
完璧な旅は「完璧な準備」から。
ぜひこのガイドを活用して、あなたのスイス旅行が思い出深いものになりますように。ルールを知れば、スイスは誰にとっても「自由で心地よい国」になります。